|
反省なき犯罪者、金儲け主義の出版社
なにより私が問題だと感じたのは、「手記」の出版を自らが出版社に売り込んだという点。犯行に至る動機等は通常裁判の過程で明らかにされるものだし、そこで語られるものだ。しかし、最近は裁判で犯行に至る動機や、その過程が明らかにされることは少ないように感じる。法廷戦術なのかどうかは不明だが、弁護側もすぐ心神耗弱その他を主張して精神鑑定に持ち込む傾向が強いのは納得しかねる部分がある。似たような事件の再発を防ぐ意味でも、きちんと動機の解明と犯行に至る過程を明らかにすることにこそ重点が置かれるべきだと思うが。
神戸連続児童殺傷事件の加害男性は「手記」で上記の点を明らかにしたのかといえば、どうもそうでもないらしい。では、なぜ「手記」を出版したのか。しかも被害者遺族への断り、事前連絡もなく、一方的に。
一般的にこの種の「手記」が出版される場合、出版社側からの働きかけによることが多い。ところが、今回の場合は加害男性からの働きかけにより実現したようで、この点でも異色だ。見方を変えれば加害男性が社会に周知させたい「なにか」が強くあったということだろう。それは犯行に至る動機、犯行の結果に対する強い懺悔の念、と考えるのが一般的だろうが、上記の過程を見る限り、そうではないようだ。
自らが犯した罪を直視し、真摯な反省を行っているというよりは、別のなにかを感じてしまう。例えば自己顕示とか金銭的な側面を。
当時犯行に及んだ加害者もいまは32歳。犯行時未成年者であったとしても、いまはすでに「少年A」と記されねばならない年齢ではないが、自ら「少年A」と記し、幕の向こう側にいようとしている。
「少年A」――それが、僕の代名詞となった。
僕はもはや血の通ったひとりの人間ではなく、無機質な「記号」になった。
この書き方にも違和感を覚える。もしもまだ「塀の中」にいるならともかく、すでに社会復帰し、年齢も30代の成人である。もし真摯に向き合うつもりなら「かつては『少年A』と呼ばれた○○」と自らの氏名を名乗るという方法もあったのではないだろうか。それはリスクがありすぎると思うなら、出版という形は取るべきではなかったと思うが。
もう一つの疑問は「絶歌」というタイトル。このタイトルは彼の強いこだわりから付けられたらしいが、文中でその理由を明らかにされることはなかったようだ。そこまでこだわったタイトルなら「あとがき」ででも触れるように出版社側から彼に指摘してもよかったように思うが、それもなかったようだ。
どうもこの「手記」に関して出版社の意向はなかった、単なる印刷屋に徹したような感じがする。早い話が商業主義一辺倒で、「少年事件は金になる」とばかりに「出版する」ことが最大の目的ではなかったのだろうか。いかなる言葉で繕おうとも。
「表現の自由」「知る権利」の名の下に、このところ出版社が「禁じ手」を次々に繰り出し、それに乗る形で精神科医までもが内部資料を披露し、著書を著しているが、彼らが言う「表現の自由」「知る権利」は単なる隠れ蓑であり、本心は「儲かる」からやっているだけとしか思えない。
最近の出版社に文化の担い手という意識が希薄になり、ひたすら金儲けの商業主義に走りだしている。売れればなにをしてもいい、売れることが正義だとでも言いたげな風潮が出版界の一部にあることを憂う。
歴史は繰り返す−−。最近とみにこの感を強くしている。「金を儲けることは悪いことですか」。村上ファンドの村上世彰氏が言い放った言葉が既視感のように現れてくる。
もちろん、こうした人間ばかりではないことは分かっている。「公益資本主義」を唱える原丈人氏のような人もいる。
私の友人(現在沖縄にいる)にも九州が豪雨、岡山県で台風の被害が出ているというニュースを見れば心配して電話をかけてくれる男がいる。なにもなくても1、2か月に一度は必ず連絡をしてくる。10数年前、私から借金をした直後に連絡が取れなくなったことがあったが、10年後にひょっこり電話があり、「農業関係の仕事でラオスに行っていた。借りていた金を返したい」と言い、それから毎月きちんと返済してきた。返済が終わってからも定期的に連絡をくれる。別に頼んだわけでもないが、彼の性格なのだろう。いまは沖縄にいるが、彼とはそんな関係がいまも続いている。
かと思えば平気で嘘をつく人、約束を守らない人、その場を繕うことのみを口にする人もいる。総じてジコチュウ(自己中心主義)が増えているように感じだしたのが私の思いすごしならいいのだが。
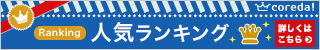

|



